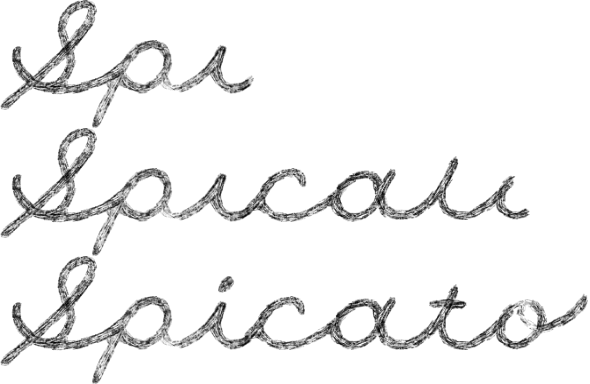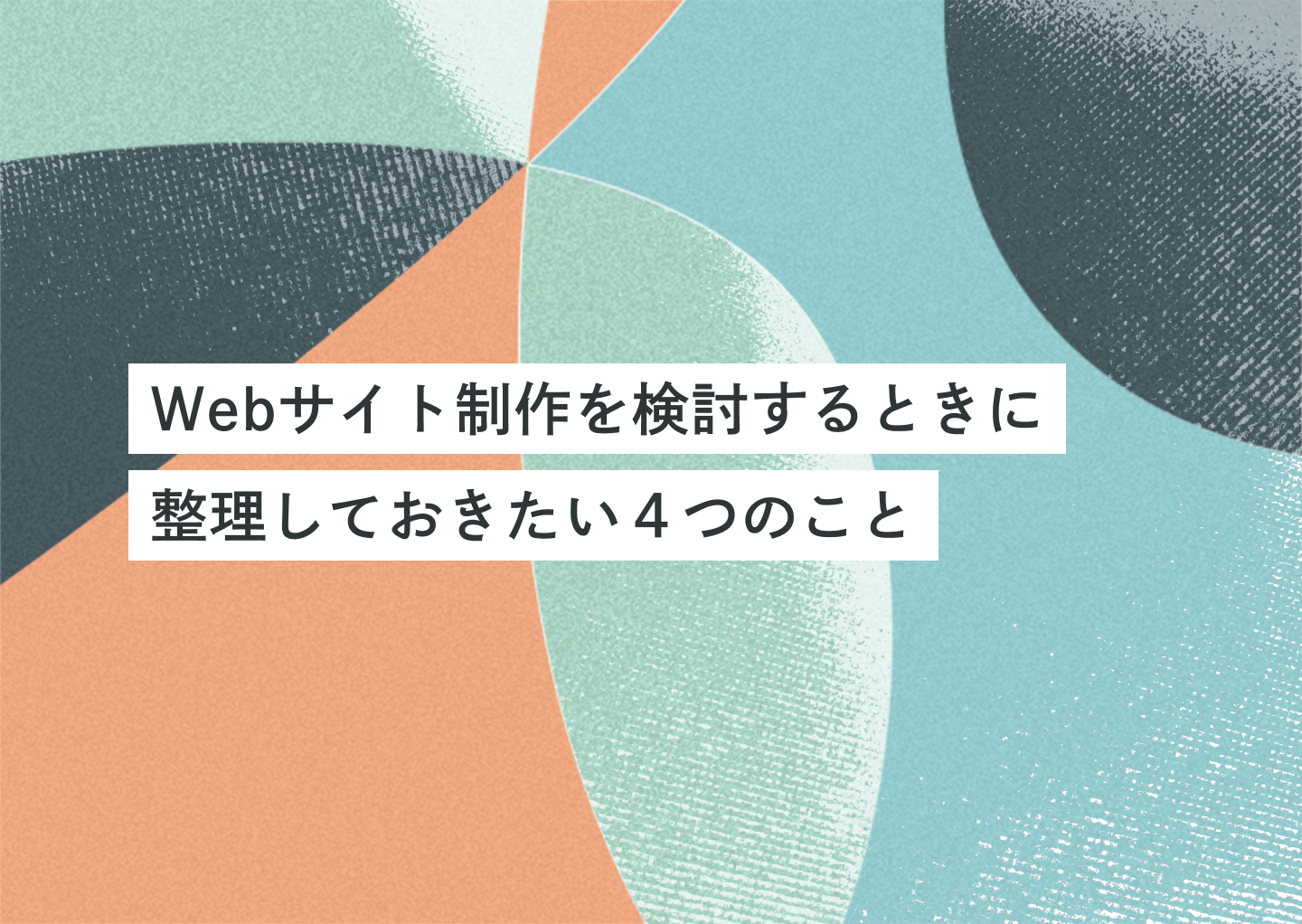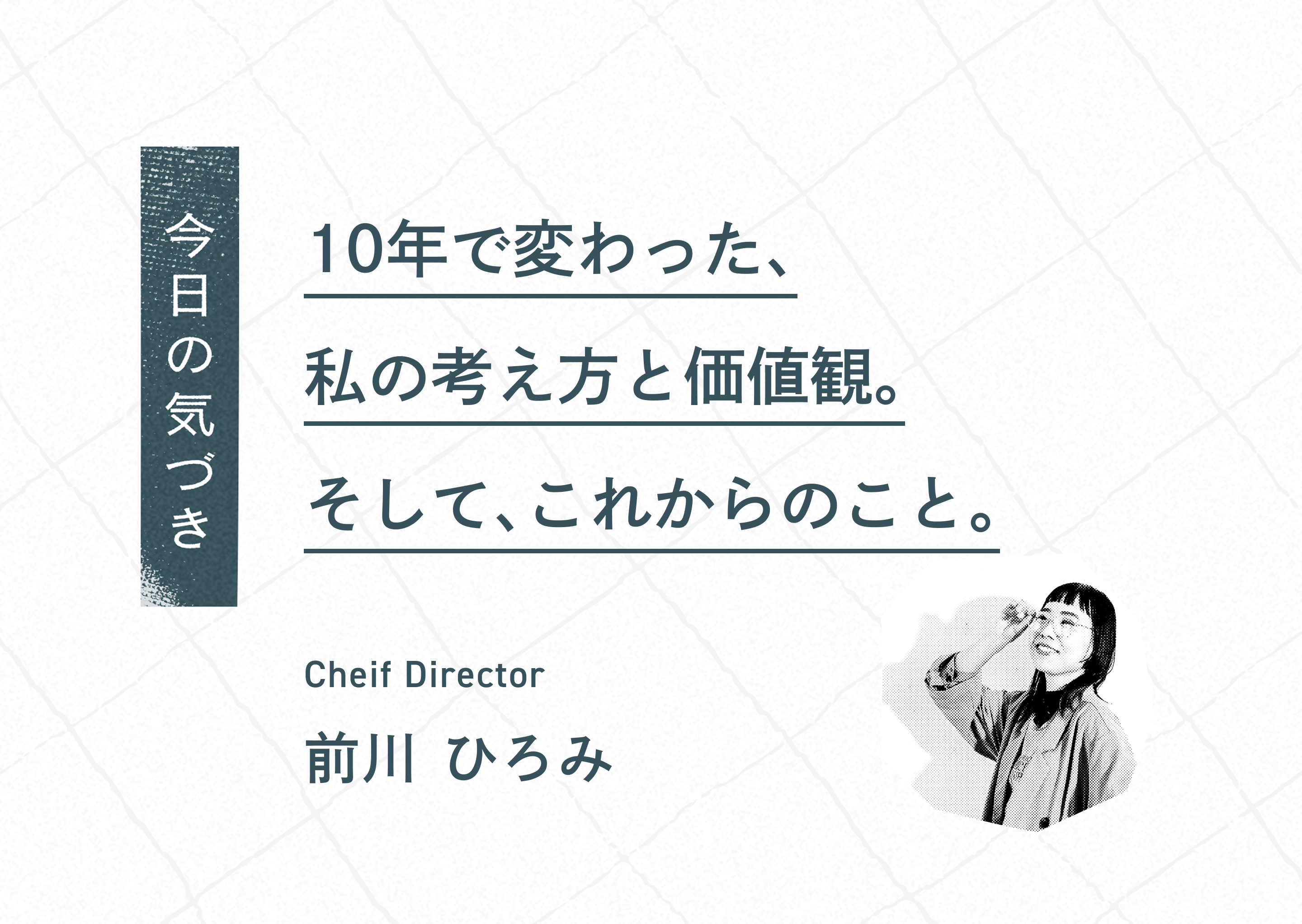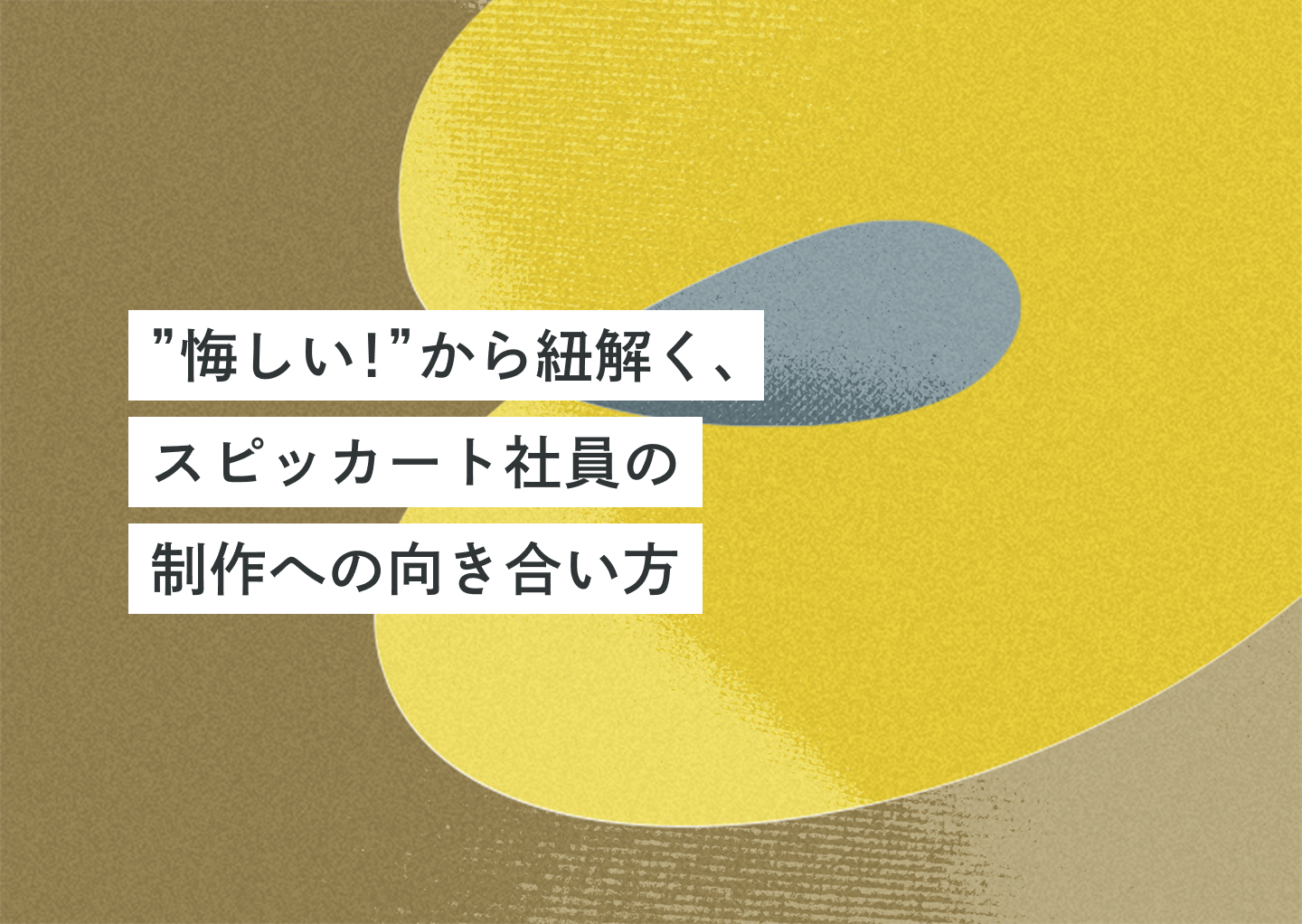誰かの”悔しい!”を久しく聞いていない。
学生時代は日常茶飯事だったのですが、歳を重ねるごとに自分の感情とうまく付き合えるようになってきて、突発的に悔しさをぶつける・ぶつけられる体験が少なくなりました。
大人になれたのかな?と思うけれど、私はその感情を隠す行為を必ずしも良いことだと捉えたくはありません。それでも前に進む力を悔しさが与えてくれるからです。
”悔しい!”感情が生まれた背景には、いつも「大切にしたい信念」があるように思います。
今回は私竹内が、4月入社の「まだ新顔」の立場を利用し、社員の皆さまに「スピッカートに入社してから経験した”悔しい!”エピソード」をインタビューさせていただきました。
常に自分のできる最大限と向き合っている以上、もどかしい気持ちも必ず生まれているはず。
”悔しい!”エピソードを通して、皆さまはどのような信念をもってお仕事をされているのか、覗いてみたいと思います。
技術の階段の数を見誤った!
初めて一人で任されたお仕事のときに、自分の力不足で期日通りにコーディングの実装が進まず、手伝っていただきました。
前職でプログラミングの経験はあったものの、モーショングラフィックやWordpressを利用した遊び心のあるサイトのコーディングには慣れておらず、時間を要してしまったのです。技術の階段が1段ではなく10段以上あることに、なかなか気づくことができませんでした。
あのときは何故か「ひとりでやり切らなきゃ!」とプレッシャーと孤独に苛まれながら作業をしていました。相談をすることで、問題の解決はもちろん心のリソースを確保することにもつながります。この出来事があってからは積極的に先輩たちに相談するようになりました。
(デベロッパー/安藤)
報連相のラインとタイミング
スキルアップにつながりそうなお仕事を任されたとき。問題が発生した際に自分ひとりで解決しようとしてしまい、結果リーダーに仕事を巻き取っていただいたことがありました。
悔しいのはもちろんですが、申し訳ないという気持ちも大きかったです。あのときは「人に聞いても良いライン」がうまく掴めていなかった。
それからは手を動かす前にスケジュールを立て、もし遅れるようなことがあればその日のうちに相談するようにしています。そのとき、相談事項を具体的に伝えることも大切ですね。
たくさんの悔しい出来事を経験して感じるのは「悔しい」思いをすればするほどその後成長できるということ。やっぱり挑戦して、失敗してを繰り返すのが大切なんだなと思います。
(デベロッパー/笠井)
情熱と冷静さの両立
計画性や技術力の不足により、自分ひとりで案件をこなしきれなかったことがあります。
新しいチャレンジもあり、技術を会得しながら制作に励みましたが自分の力では日数が足りず、最終的にリーダーにバトンタッチすることになりました。
制作への情熱はもちろん大切ですが、全体を見通して冷静に判断することの重要性をここで学びました。その後の反省会の内容も踏まえ、現在はタスクを細かく分解してリストを作ったり、「これ以上悩んだらもったいないセンサー」を研ぎ澄ますようになりました。
周りの皆さんにもご迷惑をおかけしてしまったのですが、自身の成長にもつながった大切な出来事だと思っています。
(デベロッパー/鍋谷)
自分が成長するたびに反芻する悔しさ
自分が成長するたびに、入社してすぐの案件を思い出しては「もっとやれただろうな」と悔しさがリバイバルしますね。
ギミック量の多いサイトだったので、今着手すればもっときれいに実装できたと思う箇所がいくつもあります。未経験から初めての仕事で時間もたっぷりかけた案件だったので当時は達成感がすごくあったんですけど。Web業界のことを知っていって経験が増えていくたびに「あの部分こうできたな…」と毎回この出来事を反芻して悔しい気持ちが大きくなっていくので、これ以上悔しい出来事は起こらないんじゃないかなって思っています。
(デベロッパー/金山)
「これは任せて!」を見つけたい
入社して日が浅く仕事量も調節していただいているので、悔しいことがまだ生まれづらい状況にあります。強いて言えば、この新人状態から早く脱したいと感じるのが悔しいと思うことでしょうか。
ですが、余裕のある今だからこそ「どうすれば説得力のあるご提案ができるのか」「どんな情報設計だと、お客さまの目的が達成できるサイトになるのか」など課題一つひとつに向き合うことができているとも感じます。
これから悔しい出来事があっても、そこから生まれた新しい課題に真摯に向き合い、お客さまにご満足いただける提案ができるディレクターになれるよう頑張ります。
(ディレクター/野田)
「お客さまと二人三脚」を抜かりなく
初回のデザイン提案のとき、「お客さまらしさ」を表現しきれなかったことがあります。
お客さまからの期待に応えようという気合いが空回ってしまったことと、参考にしていたWebサイトの雰囲気に照準を定めすぎてしまったことが原因だと感じています。
「ご提案する前に気付けたな」って今でも悔しい。ディレクターはお客さまと見据えるべきゴールを一緒に見つけ出し、課題を解決するお仕事です。お客さまが訴求したいターゲット層にどう見せたいのか、お客さまがこれからどうありたいのかをしっかり考えていくことを徹底していこうと改めて実感した出来事でした。
(ディレクター/前川)
自分では良いと思ってても…
ここ一年ずっと悩んでいるんですけど…。お客さまの要望通りのデザインをご提案する難しさと日々格闘しています。
「これだ!」と思うデザインを提示しても、先輩デザイナーさんに見せるとふりだしに戻るようなご指摘をいただくので、それに気付けない自分が悔しくて。
視野が狭くなるのが自分の良くないクセなので、先輩デザイナーさんに見ていただく機会をもっと増やそうと思っています。お客さまの心が弾むような提案をするために、表現の幅も増やしていきたいですね。悔しくてどうしようもないときは誰もいない道で「悔しいー!」と声に出して帰っています(笑)
ウェブサイトでもグラフィックでも自分のイラストを使ったお仕事で活躍したいので、研究を怠らずこれからも頑張ります。
(デザイナー/田中)
いろんな憂いごとが一度のミスをきっかけに押し寄せた
撮影進行のリードがうまくできなかったことがあります。
ただ力不足だったというわけではなく、技術面での慢心や、自分のスピッカートでの立ち位置について漠然とした不安があって。それを少しずつ募らせた結果のしくじりでした。
いつもの自分じゃないことに気がついてくださったディレクターさんに相談することでかなり心の整理がついて、自分が抱えている問題について冷静に向き合うことができました。
今では撮影の前日に心配や緊張感があると逆に安心しています。地に足ついているなって。これからも慢心することなく成長していきたいです。
(デザイナー/白瀧)
もうひと押しのこだわり
自分が担当した案件の次年度の担当に違うデザイナーが指名されたことがあります。
手塩にかけて育てた案件だったので、すごく悔しかったな。
うまく方向性が定まらなかったことや迫る締め切りへの焦りもあって「とにかく案件を進めなければ!」と立ち止まって考えることができなかったことが原因だと感じています。
それから「急がば回れ」を意識するようになりました。悩む時間をもっと作るようになったり、こだわりたい部分を常に明確にしながら仕事を進めたり。この出来事がなければ現状に甘んじていたかもしれません。
指名されるようなデザイナーを目指して頑張ります。クオリティは嘘をつかない!
(デザイナー/米田)
お客さまがどうありたいのかまで見据えること
お客さまの要望に沿うデザインをなかなか提案できなかったことがあります。
なぜそうなってしまったのかを考えたときに、お客さまのなりたいビジョンをふまえたデザインができていなかったことに気がつきました。そこで、デザインの提案を一旦やめて「言葉のみのやりとり」へ立ち返ることに。お客さまとスピッカートが目指す共通のゴールが明確になり、軌道修正することができました。
綿密なヒアリングを重ね、お客さまと共にデザインを作り上げていくことの大切さを改めて実感した出来事でした。
(シニアデザイナー/井上)
もどかしく感じることもあるけれど
自分もデザイナーとしてやってきているので、仕事をアサインしながら「この案件、自分がやりたかったな」と悔しくなるときもあります。自分が手を動かせる分、もどかしく感じる部分もあるというか。ですがそこはスピッカートの代表として、スピッカートがお客さまへご提案する「デザインの質」をどう上げていくか、という視座で考えています。これからもデザイナーをはじめ、スタッフ全員が一歩ずつ成長できるよう見守っていきたいですね。
(CEO/細尾)
みなさま、ありがとうございます。
物事に真剣に向き合っていないと” 悔しい!”という感情は生まれません。自分が担当する案件に常に真摯に臨まれていることが、ひしひしと伝わるインタビューでした。
「今でも悔しい」と当時を振り返る方も多くいましたが、それでも清々しくお話されていたのが印象的でした。会社の中で日々の悔しさや悩みを受け止め、消化できる環境が整っていることが大きな要因なのだと思います。
スピッカート社内は常にやわらかい言葉で溢れている職場です。お昼どきにふらっと集まって突然始まる井戸端会議や、お仕事中ふと聞こえる面白話(耳を澄ませていてすみません)が「お客さまと念入りに話し合いを重ねる」「積極的に周りに相談する」というコミュニケーションを交えた解決方法に至っている要因のひとつなのかもしれません。
これから進捗や質問、日々の気付きまで積極的にコミュニケーションをしようと思えるインタビューでした。
spicatoの制作に対する情熱。少しでも感じていただけたらうれしいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
竹内でした。