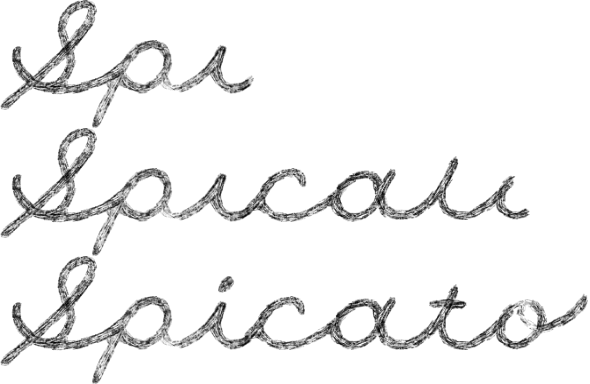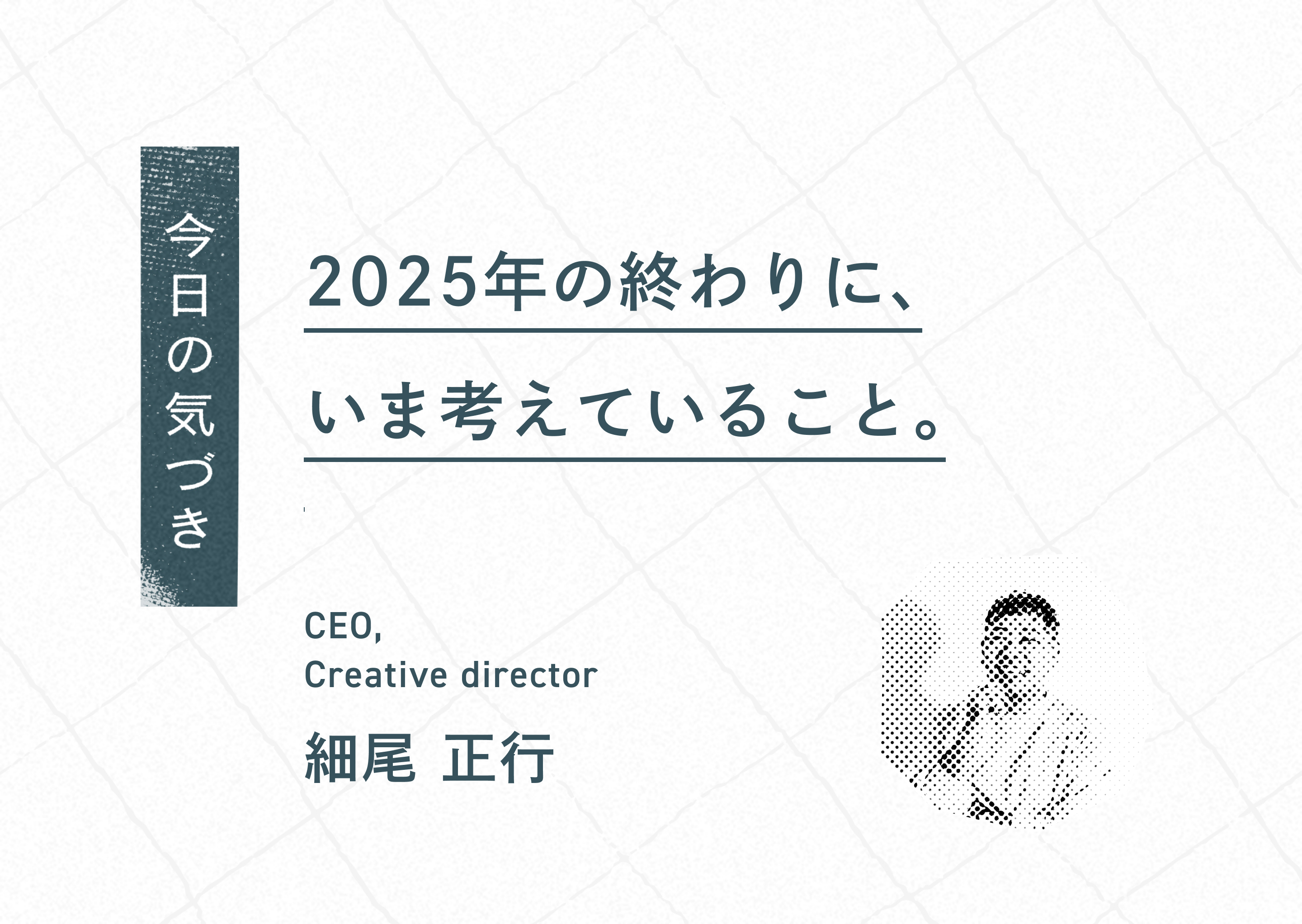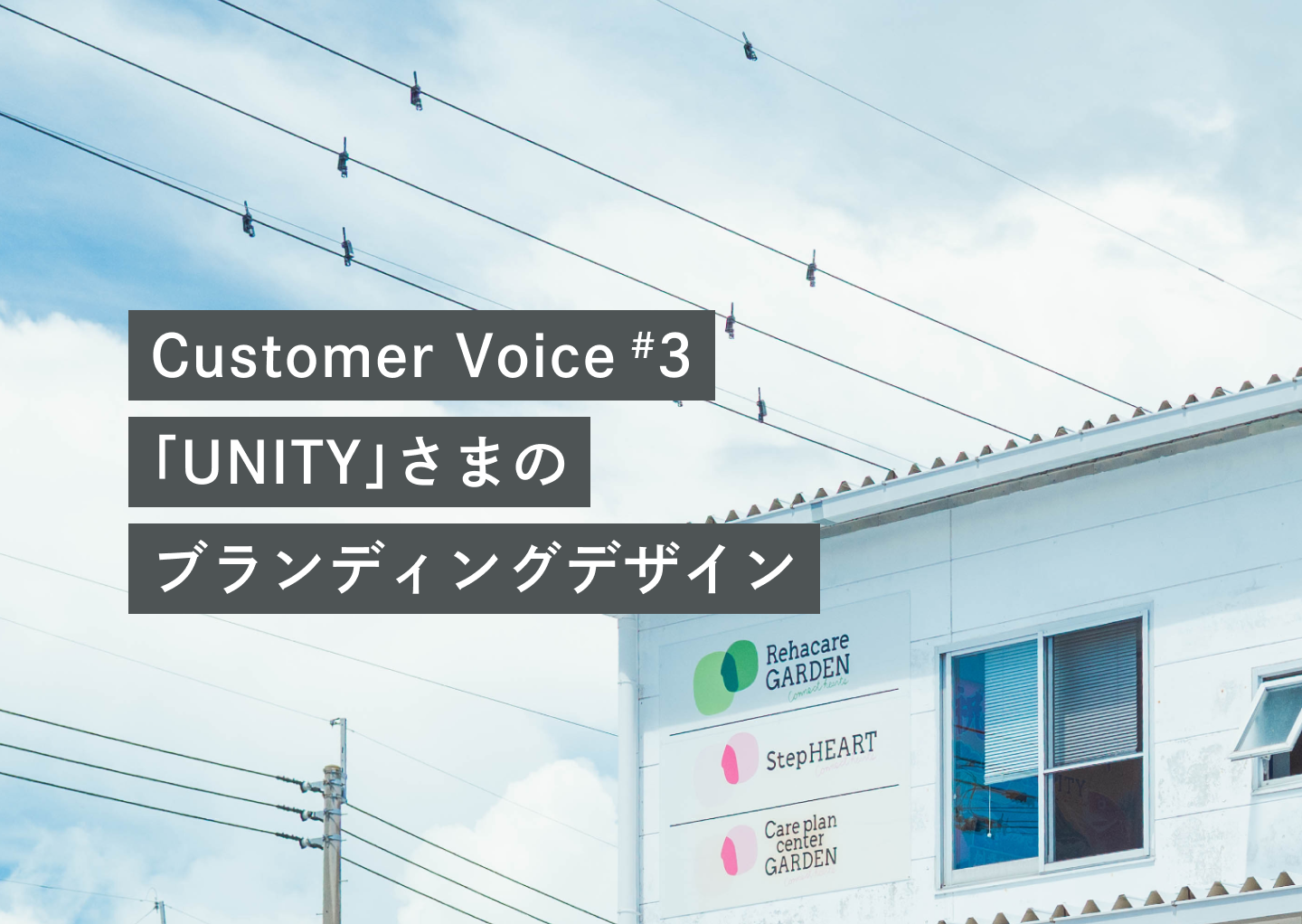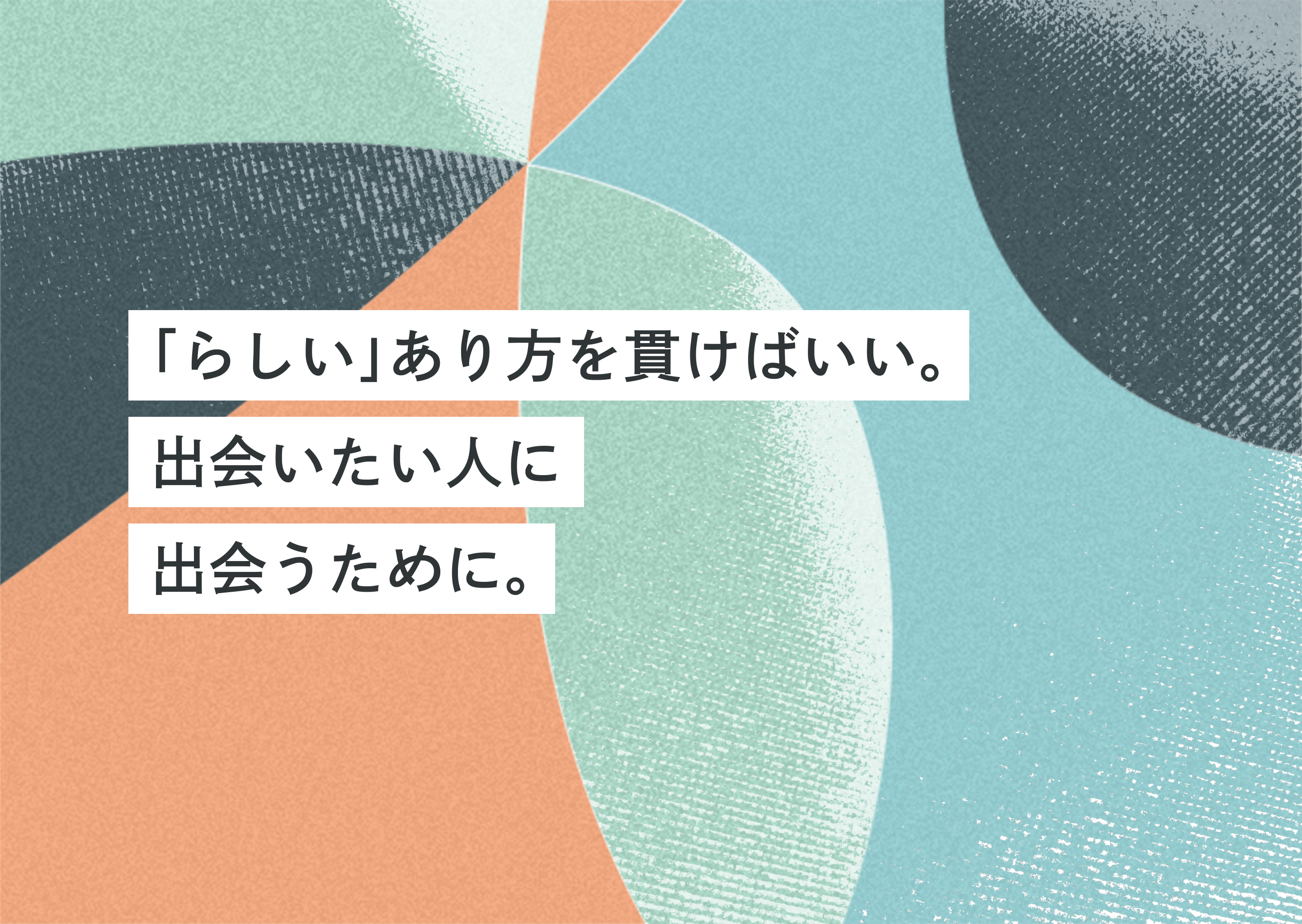制作物の価格を載せない、旧サイトほどスタッフを前面に出さない、Webサイトのみならず、チラシ、ポスターなどのグラフィックも含め、トータルでデザインを引き受けられるイメージを出す……。先日リニューアルしたWebサイトでは、クライアントとのミスマッチを減らしていくためにテイストや見せ方を変えたスピッカート。
いくらデザインを気に入ってもらえても、価値観や志向性、望んでいるものがクライアントと異なっていれば、制作過程ですれ違いが生じるなど、望ましい結果を招かない。そんな実態をもとに見つめ直した制作会社とクライアントの“理想の関係”とは?
参加者
- 細尾:スピッカート代表。2008年に独立し、2016年にスピッカートを法人化
- 前川:2015年にスピッカート入社。4年目にはデザイナーからディレクターに転身。
- 笠井:2022年に未経験のWebデベロッパーとして入社。公式SNSをはじめ広報も担う。
満足度の高いものをつくりたいから
細尾:Webサイトであれ紙媒体であれ、僕たちが大切にしているのは、制作物を通してお客様のらしさやオリジナリティを最大限表現すること、「ずっと変わらない軸」となるようなものをつくることです。
なので、たとえば同じ業界、業種のお客様でもまったく違ったテイストの制作物に仕上がります。それはあえて違いを創り出そうとしているわけではなく、じっくり対話を重ねてお客様のらしさを理解していけば、おのずと違うものができあがるという感じです。
ただし、そのプロセスにはお客様の“協力”が欠かせません。お客様へのヒアリングを通してじっくり目的を掘り下げたり、認識のずれをすり合わせたりすることなくして、想いの核心やオリジナリティはなかなか見えてこないからです。その中で、お客様自身が気づいていなかった魅力に気づかれることもあります。

前川:時間や労力をかけてでもいいものをつくりたいというモチベーションがお客様の中になければ、ご期待に沿えない結果になってしまう可能性が高いと思います。
細尾:初回の打ち合わせ時点で、会社の紹介資料の他、制作物を通じて実現したいこと、ベンチーマークにしている企業やサービス、参考にしたい言葉やデザインなどを出していただけるとスムーズに進められます。いわば、求職者が働きたい会社の選考に備えて自己分析をするようなものでしょうか。
お見積りは基本的に、2パターンお出ししています。お客様からいただいたご予算に即したお見積り(プランA)と、予算は超えるけれども、お客様の要望を最大限叶えうるお見積り(プランB)です。
その両案をもとに、多少我慢してでも予算を優先したいか、あるいは予算をオーバーしてでもいいものをつくりたいかは、もちろんお客様次第。これまでの経験上、「Aのままで」という方は少なく、AとBの間に収まるケースが大半ですね。
ある意味、結婚式に近い感じかもしれません。予算内に収めたいところだけど、一生に一度の晴れの日なんだから、相手を喜ばせたい、遠くから来てくれる家族や友人を楽しませたいと思えば、奮発したくなるものですよね。制作物も同じで、お客様もせっかくなら満足度の高いものをつくりたいでしょうし、こちらとしてもできる限りのことをさせていただきたいと思っています。
前川:私自身、仕事で携わっている立場でありながらも、制作過程で自然とお客様のファンになっていくことは多いんですよね。はじめはまったく知らないブランドだったのに、積み重なってきた背景やこめられた思いに触れているうちに、プライベートでもそのブランドの商品を買い、イベントに参加するように変わっていく。仕事であっても、そこまで入れ込めるのは幸せだなと思います。
来てほしいお客さんに来てもらうために
細尾:自分たちのやりたいことを基軸にせず、顧客ニーズだけに合わせて変化していく方も、僕たちとはミスマッチかなと感じています。ただ、そのやり方を批判するつもりはまったくありません。広告を打つなり、SEO対策を徹底するなりして、PVやコンバージョンを増やすことを目的にするのは単純に僕たちの得意分野ではないからです。もしそういったところがご希望であれば、他の制作会社さんをおすすめします。
前川:私たちがつくったデザインや言葉に対して、いいよね、かわいいよね、素敵だよねと見た人たちが感じることで、その会社やブランドのファンができる、あるいは社員さんのモチベーションが上がる。それが、私たちがお客様とともにつくっていきたい未来です。
たとえば、営業担当者が「使いやすくなった」「デザインが素敵になった」という理由でWebサイトをお客様に積極的に見せるようになり、成果にもつながったケースは少なくありません。お客様からも「サイト素敵ですね」と褒められた喜びが、別の営業先に向かう足取りを軽やかにすることもあれば、新しい事業を始める原動力になることもある。このサイトが好き、誇らしいという気持ちが、自然と行動に変わっていくんです。その変化は定量化しにくいけれど、結果的には売上や収益などの数字に表れてくると思います。
細尾:当社でWebサイトをリニューアル後、問い合わせが増えたお客様やPV数が500%以上に伸びたお客様もいらっしゃいますが、そこを打ち出そうとは思っていません。お客様からは「スピッカートさんに頼めば自分たちの世界観を発信できるから、お客さんをフィルタリングできる。要は、来てほしいお客さんが来てくれる。数字にフォーカスすれば、お客さんの数も売上も増えるかもしれないけれど、それは僕たちが求めている満足とは違う」という声もいただいています。
笠井:デベロッパーとしてスピッカートで働くこと約2年、私個人としては全国1000万人以上のユーザーが使う最大公約数的なシステムをつくっていた前職よりもやりがいがあります。直接お客様と接する機会はあまりないけれど、他のメンバーからお客様の声を教えてもらったり、お客様のSNSに届いた反響を見たりして、出会いたい人に確実に出会えている手応えを感じられるんです。

つくることに燃え続けて
細尾:内情を明かすと、スピッカートの経営は綱渡り的です(笑)。Webサイトを制作した後の保守、運用やコンサルティングをひとつの柱にして、毎月定額料金をもらえば経営は安定するのですが、これまでそこにはあまり軸足を置かず、制作物をつくり続けてきました。
つくりたくて仕方ない人たちが集まっているからか、常に新しい何かと戦いたい気持ちが僕たちの根底には流れています。社内のメンバーにも「お客さんが認めるまでデザインは1にならない。いくら時間をかけてつくっても0やで」と話していますが、納得いくまではお客様にデザインをお見せしません。
その源流には、昔のWeb制作会社の主流に対するアンチテーゼがある気がします。15年ほど前はホームページのテンプレートを使って画像を差し替え、運用費で儲けるお手軽なビジネスが盛んだったのですが、その流れに乗りたくない、ユニークでありたい(人と同じことを嫌う)気持ちが強かったんです。スタッフも似たようなマインドを持っているので、以前、自社PRの一環として、皆でおそろいのボーダーシャツを着て撮影したときはブーイングの嵐でした(笑)。
前川:ここ数年は、自分たちのオリジナリティを出したい、他とは違うものにしたいというニーズを持ったお客さんも増えてきています。標準的なデザインを求められないので大変ですが、その分やりがいがある。
細尾:逆に「よくある感じでつくってください」、「このデザイン通りにつくってほしい」というリクエストをいただいたら、内心がっかりしてしまいます(笑)。せっかく料理をするなら、レシピ通りにつくったり、お惣菜を使ったりするんじゃなくて、とれたての野菜をもとに考えたいんですよね。その野菜でユニークかつおいしい創作料理をつくるのが、僕たちの腕の見せどころでもある。
数字を最優先しなくても結果は出る
前川:だからといって、数字を悪者にしたいわけじゃないんですよ。以前、当社でWebサイトをリニューアルされたお客様に、その後の進展について聞いたところ、こんなメッセージを送ってくれました。
「依頼前は、欲を言えば新規顧客を増やしたい、検索すれば一番上に出てきてほしいと思っていた。でも、それが目的になって伝えたいメッセージが薄まってしまうより、シンプルであたたかみがある今のサイトの方が自分たちに合っていると思う」と。
細尾:あくまでもこれは相性の問題。ある意味お客様を選んで、共感、共鳴できる人どうしでビジネスをした方が、お互いにとって幸せだと思うんです。
逆に、いくら注目度が高まって売上が上がっても、文句を言う人や高圧的な人に対応しなければならないのなら、企業として大きな損失になってしまう。たとえお客様であっても、対等に意見交換できて、お互いにいい関係を育み合える方が健全かなと。
いや、ビジネスをやっている限り利益を出さないといけないので、選びたくても選べない、断りたくても断るのをためらう気持ちはわかります。会社の先行きが不安だから、成果は目に見える数字として明確に表れた方が安心できるのもわかります。
それでも僕たちが数字を追っていないのは、結果がついてきたからでしょうね。2008年にスピッカートを創業後も、2016年に法人化した後も、数字に頼った経営はしてこなかったけれど、ずっと右肩上がりで成長を続けているし、喜んでくださるお客様も増え続けている。
きちんと評価してくれるお客様や、深いところで共感できているお客様と仕事をすることは、あらゆる面でプラスに作用する。身に沁みてそう感じているからこそ、自分たちの「らしさ」を信じることから世界が開けるよろこびを、僕たちに依頼してくださったお客様と分かち合いたいんですよね。

Interview & Writing: Screen 中道達也